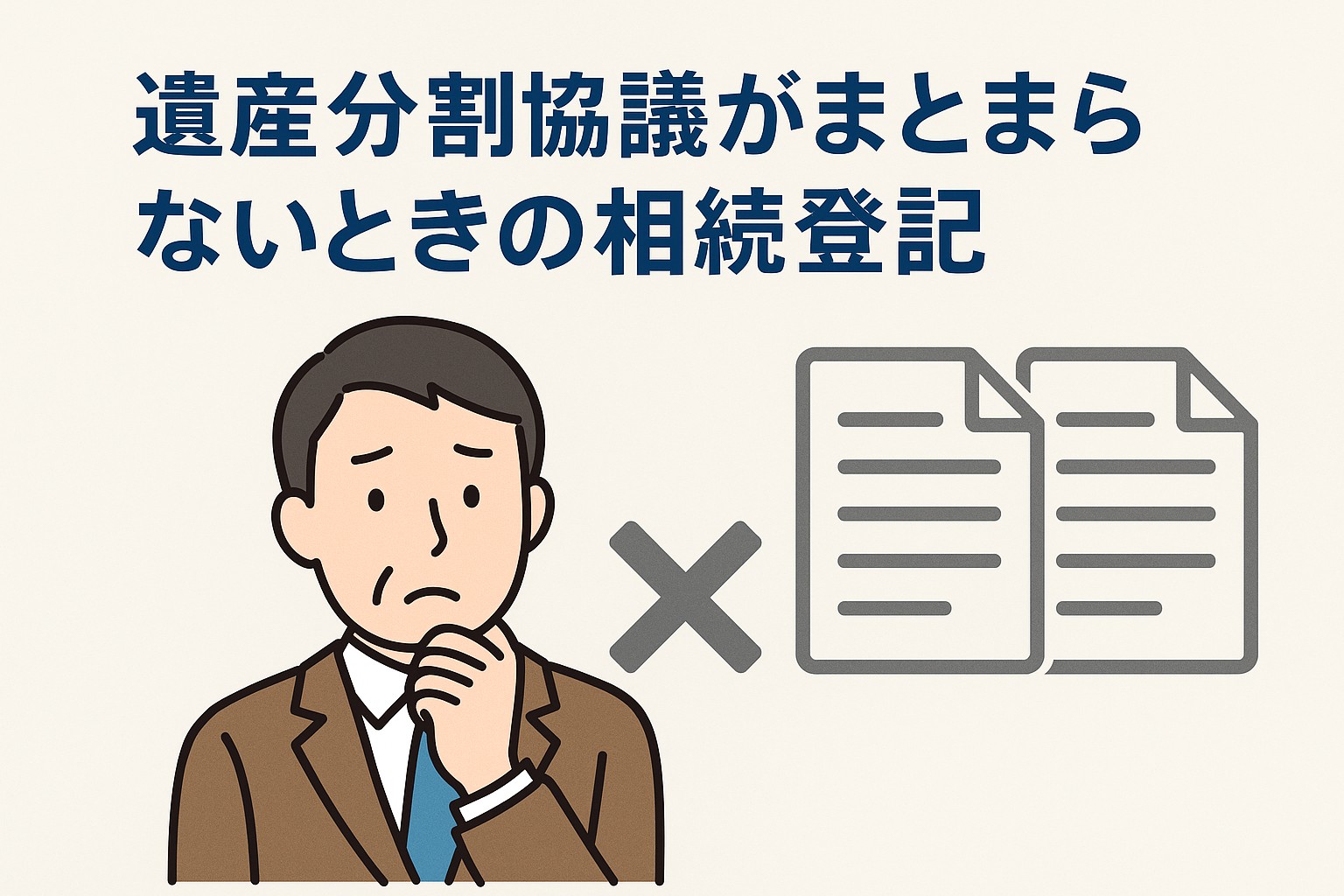こんにちは、とのさき司法書士事務所の外崎です。
相続登記が義務化されて「やらないといけない」と思っていても、
実際にはこんな理由で手続きが止まってしまうことがあります。
「きょうだいで話がまとまらなくて…」
「1人だけ連絡に応じてくれない相続人がいて…」
こういった状況でも、できることはあります。
この記事では、「遺産分割協議がまとまらないときの相続登記」について、実務的な対処法と義務化への対応方法を解説します。
義務化されたのに、協議ができない…どうすれば?
2024年4月から、相続登記は義務化されました。
相続が発生してから3年以内に登記をしないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。
でも「登記したくても話がまとまらない」というケースは少なくありません。
そこで、いま取れる選択肢を整理しておきます。
対応策① 法定相続分による相続登記を先にする
遺産分割協議がまとまらなくても、相続人全員が法定相続分どおりに不動産を共有する形で登記することは可能です。
【例】
相続人が2人で、協議ができていない場合:
→ とりあえず「1/2ずつ共有名義」で登記する
この方法であれば、とにかく登記義務は果たすことができるので、義務化に対するリスク回避になります。
もちろん、あとから協議がまとまれば、その時点で共有状態を解消する登記も可能です。
対応策② 相続人申告登記で最低限の義務を果たす
2024年から新たに始まった「相続人申告登記」という制度を使えば、
「自分が法定相続人です」とだけ申告する形で、登記義務を満たすことができます。
この手続きは、遺産分割協議が終わっていなくても単独で可能です。
登録免許税もゼロ円なので、費用面でも安心。
あとから分割協議が成立すれば、改めて所有権移転登記をすればOKです。
対応策③ 不在者や連絡不能者がいる場合は家庭裁判所を使う
話し合いができない相続人がいる場合(行方不明・返事がないなど)は、
家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申し立てたり、遺産分割調停を利用する方法があります。
やや時間はかかりますが、最終的には法的に登記を完了できるルートです。
対応策④ とにかく「放置しない」ことが大事
「まとまらないから…」といって何もせずにいると、次の世代にさらに相続人が増えてしまい、
相続人が10人以上になる“数次相続”状態になることも珍しくありません。
そうなると、相続登記はさらに複雑に、費用も時間もかかるようになります。
とのさき司法書士事務所では…
当事務所では、次のようなご相談も日常的に対応しています。
- 一部の相続人と連絡が取れない
- 揉めるほどではないけど話し合いが進まない
- 申告登記と共有登記、どちらがいいのか迷っている
状況に応じて、“今できること”と“将来的にすべきこと”を整理してご提案しています。
まとめ
- 遺産分割協議がまとまらなくても、できる手続きはある
- 法定相続分での登記 or 相続人申告登記で義務化に対応できる
- 行方不明者がいる場合も、家庭裁判所の手続きを活用できる
- 放置するほど将来の手続きは面倒に。早めの対応が吉!
📩 「うちの事情では無理かも…」と思っている方も、まずはご相談ください。
現実的な選択肢を一緒に考えていきましょう。